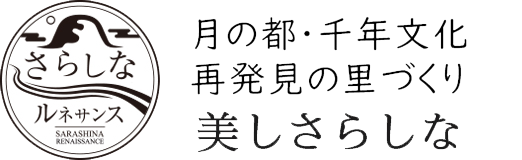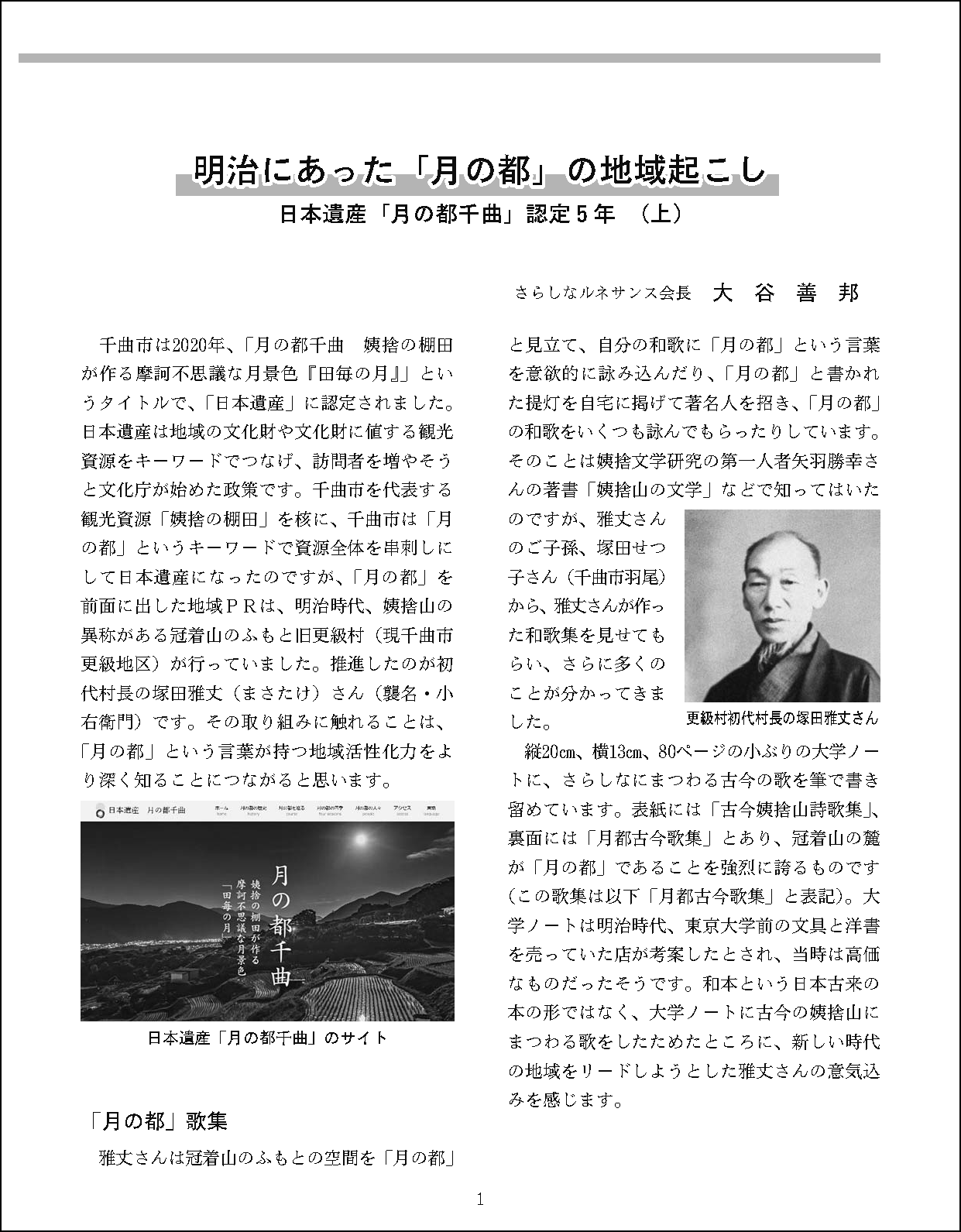
2025年は信州千曲市が「日本遺産」に認定されて5年。長野県地方自治研究センターの機関誌「信州自治研」に、「月の都」について2回にわたって寄稿する機会を得ました。1回目は9月号。明治の更級村村長が行っていた「月の都」による地域起こしについて書きました。2回目は10月号で、本会が千曲市日本遺産推進協議会と連携して行うようになった「月の都」の魅力の深掘り事業を紹介する予定です。後日アップします。(画像をクリックすると、PDFが現れ、印刷できます)
なお、「信州自治研」には8年前、本会発足の背景や経緯、狙いについての文章も寄せています。https://sarashina-r.com/?p=2153
明治にあった「月の都」の地域起こし
日本遺産「月の都千曲」認定5年(上)
さらしなルネサンス会長 大谷善邦
千曲市は2020年、「月の都千曲 姨捨の棚田が作る摩訶不思議な月景色『田毎の月』」というタイトルで、「日本遺産」に認定されました。日本遺産は地域の文化財や文化財に値する観光資源をキーワードでつなげ、訪問者を増やそうと文化庁が始めた政策です。千曲市を代表する観光資源「姨捨の棚田」を核に、千曲市は「月の都」というキーワードで資源全体を串刺しにして日本遺産になったのですが、「月の都」を前面に出した地域PRは、明治時代、姨捨山の異称がある冠着山のふもと旧更級村(現千曲市更級地区)が行っていました。推進したのが初代村長の塚田雅丈(まさたけ)さん(襲名・小右衛門)です。その取り組みに触れることは、「月の都」という言葉が持つ地域活性化力をより深く知ることにつながると思います。
▽「月の都」歌集
雅丈さんは冠着山のふもとの空間を「月の都」と見立て、自分の和歌に「月の都」という言葉を意欲的に詠み込んだり、「月の都」と書かれた提灯を自宅に掲げて著名人を招き、「月の都」の和歌をいくつも詠んでもらったりしています。そのことは姨捨文学研究の第一人者矢羽勝幸さんの著書「姨捨山の文学」などで知ってはいたのですが、雅丈さんのご子孫、塚田せつ子さん(千曲市羽尾)から、雅丈さんが作った和歌集を見せてもらい、さらに多くのことが分かってきました。
縦20㌢、横13㌢、80㌻の小ぶりの大学ノートに、さらしなにまつわる古今の歌を筆で書き留めています。表紙には「古今姨捨山詩歌集」、裏面には「月都古今歌集」とあり、冠着山の麓が「月の都」であることを強烈に誇るものです(この歌集は以下「月都古今歌集」と表記)。大学ノートは明治時代、東京大学前の文具と洋書を売っていた店が考案したとされ、当時は高価なものだったそうです。和本という日本古来の本の形でななく、大学ノートに古今の姨捨山にまつわる歌をしたためたところに、新しい時代の地域をリードしようとした雅丈さんの意気込みを感じます。
そこに記されている「月の都」の歌を紹介します。まず、明治22年(1889年)、 雅丈さんが主導して冠着山のふもとの羽尾、須坂、若宮の3つの村をまとめ、新しい村の名を更級村と決めたときの歌です。
君が代に月の都と言ふべきはこの更級の姨捨の山
この歌は新しい村名を「更級村」とすることを決めた直後の明治22年3月9日、信濃毎日新聞に投稿して掲載されたものです。905年に編まれた古今和歌集に載る「わが心慰めかねつさらしなや姨捨山にてる月を見て」が、さらしな里が「月の都」となる始まりの歌なのですが、この歌に盛り込まれている「さらしな」と「姨捨山」は、姨捨山の異称を持つ更級村の冠着山のふもとであることを、世の中に広く知らせようとしました。明治天皇が統べる日本の「月の都」は、さらしなの里であるという強烈な自負を感じます。
私が調べた限り和歌の歴史では、「月の都」は古くは、天体の月にある都や、月が現れている京の都のことを指して使われてきました。しかし、雅丈さんはさらしなの里やさらしなの里にある姨捨を詠んだ古今の和歌や俳句、さらに世阿弥作とされる謡曲「姨捨」の内容を知り、「月都古今歌集」を編んでいくとき、歴史上の有名人がこんなにさらしな姨捨の月をすごいと詠んできたのだから、「月の都」はさらしなの里こそふさわしいということに思いが至ったのだと思います。
一地方ではありますが、「月の都」と呼ぶ発想を得たのは、当時、政治の中心としての都が、京から江戸に移ったことも影響していると思います。西の京都に対して、江戸は東にあるので、東の都、東都という言葉もよく使われるようになりました。つまり、都というのは絶対的なものではなくなり、相対化されていたのです。そのことに気づくことができた政治家、リーダーでした。
▽「苦情これ有り候とも…」
実は更級村という村名自体が、雅丈さんの戦略的なものです。自治体合併では必ずと言っていいくらい、合併後のまちの名前を何にするかでもめますが、雅丈さんは冠着山(姨捨山)のふもとにあった羽尾、若宮、須坂の3か村をまとめる際、新村名は「更級村」で推し進めました。雅丈さんは「苦情もこれ有り候とも、わが意見を以って更級村と改称する」という言葉を文書に残しています。それくらい「更級」という地名の価値を確信していたのです。更級村という名前を世に送り出した次に村起こしとしてやるべきことは、更級村を「月の都」としてのPRすることだと考え、突き進んだのです。次はそのことがうかがえる雅丈さんの和歌です。
久方の月の都は信濃なる冠着山の峯にこそあれ
昔から「月の都」と言われてきた地は、冠着山の峰にあるという、力強い宣言です。政治的な主張が込められた歌です。当時は歌を詠むことが文化人から政治家まで有力者の大事な教養でした。
雅丈さんは当時、温泉地としてにぎわいを見せていた戸倉上山田温泉(現千曲市)に著名人が東京などから訪れるようになっていたこともあり、明治政府の要人や文化人を自宅に招き、さらしなが「月の都」だと紹介しました。「汽笛一声新橋を…」で知られる「鉄道唱歌」の作詞者大和田建樹さんもその一人で、明治29年の中秋のころ、冠着山に登った後、雅丈さんの案内でさらしなの月を堪能し、「月の都」の歌を作りました。
今よりは人に誇らんいにしへの月の都の月を見つれば
大和田さんは東京に戻り、知人友人に月の都としてのさらしなのことを語ったでしょう。
大和田さんの歌のほかにも、雅丈さんの熱意に意気投合した人たちの「月の都」を詠み込んだ歌がいくつもあります。
久方の月の都を人とはば雲の上なる冠着の山 佐藤寛
佐藤寛さんは現在の国学院大学の前身となる皇典講究所の教授だった人です。雅丈さんはこの佐藤寛さんに依頼して「古来、姨捨山とされてきたのは冠着山である」ことを証明する本「姨捨山考」を出版しました。1000部を印刷し、全国に配布しました。出版費用は自費でまかなったそうです。そうした関係のある佐藤寛ですから、雅丈さんの「「月の都」による村おこし戦略に賛同して、この歌を作ったのです。
次は、同じく「月の都」による地域起こしに賛同した石川県出身の歌人の歌です。
いにしえの月の都を人とはば雲井にちかき姨捨の山 大島浮名
大島浮名さんは、冠着山のふもとが「月の都」であることを宣伝するために雅丈さんが冠着山のふもとの里山の郷嶺山(ごうれいやま)に建てた観月殿の建設に一緒に取り組んだ人で、21歳で脱藩して諸国を流浪し、61歳のとき更級村にやってきました。剣道、和歌などを更級村の人に教えました。文人でもあったので雅丈さんの力になり、当地を世に知らしめる役割を担いました。この大島さんの和歌は、雅丈さんが大きな石に刻んで、今も歌碑として郷嶺山に建っています。
▽宮内省御歌所の職員も
こうした雅丈さんたちのPRが広まっていき、明治政府の要人や宮内省の関係者も更級村を訪れ、冠着山に登ったり、観月殿や雅丈さんの家に立ち寄るようになります。さらしなの里を「月の都」と詠んだ宮内省関係者の和歌を二つ紹介します。宮内省は明治になってできた天皇や皇室に仕える人たちの役所のことです。
仰ぎ見れば羽衣干してなり光り月の都の冠着の山 藤野静輝
藤野静輝(ふじの・せいき)さんは江戸末期、愛媛県に生まれました。東京に出て皇室の祭典や儀式などを担当する宮内省式部職につきました。詩歌や文章、書画をかくのに優れ、退官後は、歴史研究のため各地を回ったそうです。「月都古今歌集」では、この歌を藤野さんが「明治33年(1900年)観月殿で詠んだ」と記されているので、雅丈さんに案内されて冠着山に登り、観月殿で月見をしたときの歌となります。
この歌に出てくる「羽衣」は平安時代初期に作られた「竹取物語」の最終盤で、かぐや姫が月に帰るときに着た「羽衣」のことをイメージしたものです。観月殿から仰ぎ見た冠着山の嶺は羽衣が広がったように、月の光を浴びて輝いている様子を歌にしています。下句の「月の都」は、雅丈さんが村おこしで考案したキャッチフレーズの「月の都」のことですが、文芸に通じていた藤野さんは1000年前の日本で初めて作られた物語の竹取物語に登場する「月の都」のイメージを重ねたのです。冠着山とそのふもとの里の価値を一層高める歌と言っていいと思います。
もう一つ。
更級の月の都に来てみれば名にも勝ると猶おもひけむ
この歌は皇室の歌会始など歌に関する事務を取り扱う宮内省の御歌所の職員だった交野時万さんが明治36年(1903年)、雅丈さんの家と観月殿に立ち寄って詠んだ歌。更級が月の都だということに異論異議はまったくないという気持ちを歌にしています。
「月の都」の俳句もひとつ。
この舟をあがれば月の都かな 水野竜孫
水野竜孫さんは千曲市の東側に位置する現在の長野県上田市の俳人で、大和田建樹さんと一緒に雅丈さんの家で開かれた宴に同席していたので、雅丈さんの「月の都」地域おこし構想に共感して、この句を詠んだものと考えられます。上田からやってくるときは千曲川の東岸から船で渡ってきたんです。冠着山がそびえる対岸の景色を見たときの感慨を詠んだ俳句です。雅丈さんの「月都古今歌集」には、先に紹介した信濃毎日新聞への投稿掲載以後に俳人が作った「月の都」の俳句が、水野竜孫さん以外にもたくさん載っています。
▽定家の歌にヒントを得た?
雅丈さんは「月都古今歌集」に、百人一首を作った鎌倉時代の歌人藤原定家の「はるかなる月の都に契(ちぎ)りありて秋のあかすさらしな里」の歌も書き留めています。私の調べでは「月の都」と「さらしな」をセットで詠んだ最初の歌で、雅丈さんは定家のこの歌に刺激を受け、さらしなの里を「月の都」というキーワードで売り出すと思いついた可能性もあると考えています。
雅丈さんが「月の都」という言葉を積極的に使ったのは、雅丈さんの家が羽尾という千曲川を見下ろす地区にあったことも関係しているのではないかと思います。鏡台山付近から昇る月をいつでも眺められる高地に暮らしていたので、眼下に広がる奥行きのある空間は、「月の名所」よりも「月の都」と呼ぶ方がふさわしいと思ったかもしれません。
なお、残念ながら「月の都」という村おこしは、大正11年(1922)、雅丈さんが亡くなってしまうと、下火になり、電気が使われるようになって家の中も明るい時代になるにつれて、人々の月への関心自体が薄れ、続きませんでした。
▽正岡子規の「月の都」
余談です。近代俳句の創始者正岡子規に「月の都」という小説があります。講談社1976年発行の「子規全集第13巻」に載っています。これは世に打って出ようとした子規の最初の小説で、まだ俳句に本格的に打ち込む前の明治25年(1892年)、子規が26歳のときの作品です。文語調なので幾度となく読み直し、大筋は分かりました。当地さらしな・姨捨にまつわることは何も書かれていません。しかし、子規が「月の都」という言葉にどんな世界をイメージしていたかを知ることができます。
400字詰め原稿用紙で30枚弱の中編小説。好きになった女性が別の男と歩いているのを見て、出家する男が主人公です。
「美の象徴」とみなしていた女性の不義に絶望した主人公の男は、美を「月の都」に求めます。「月の都」への旅に出るのです。旅立つに当たって「理想の美人を人間に求めしこと第一の不覚」と男が言っているのが印象的です。
ではその「月の都」とはどんな所か。具体的な地名が記されているわけではありません。男の心境の大半を仏教の用語や世界観を引いて描いており、子規は仏である阿弥陀如来のいる「西方浄土」をイメージしていたことがうかがえます。
芸術の本質は美です。文芸も芸術です。明治になって文学の美とは何かということに、多くの小説家たちが関心を深めており、子規もその一人でした。26歳の時点での子規が持っていた美についての考え方がこの小説に反映していると思います。
子規が浄土のイメージをどのように持っていたか直接の資料は見つかっていませんが、26歳ごろ各地に旅をしたときに被っていた菅笠には「西方十万億土巡礼」と墨書きしています。「西方十万億土」とは経典の一つ「阿弥陀教」の中に登場する言葉で、「十万億土」というのは、はるかかなたにある極楽浄土という意味ですから、子規は浄土と自分の目指す美の世界を関係付けて旅をしていたことがうかがえます。
▽芭蕉の「月の都」
2011年に、私は千曲市観光課と一緒に「月の都」という言葉を盛りこんだ観光キャッチフレーズとロゴマークを作ったことがあります。キャッチフレーズは「芭蕉も恋する月の都」です。ロゴマークは漫画家絵本作家のすずき大和さんと一緒に作った単行本「まんが松尾芭蕉の更科紀行」の中に登場する芭蕉のキャラクターを使ったものです。満月の中に芭蕉と、芭蕉に随行した越人と権七の3人を描いています。
ロゴマークというのは地域の歴史・文化的な遺産などを踏まえイラストタッチに表現するもので、地域の現状だけでなく未来の目標を落とし込み、内外の人たちに地域への愛着を持ってもらうためのものです。これまで紹介した「月の都」の意味の変遷も調べていく中で、「月の都」はキャッチフレーズに使えると思っていたので、これまで宣伝するときに使ってきた「名月の里」のイメージを、俳聖とも呼ばれる松尾芭蕉が来訪した地であることを強調することでパワーアップしたいという狙いをロゴマークに込めました。
残念ながら今は登場しなくなってしまいました。日本遺産「月の都千曲」の前には「芭蕉も恋する月の都 千曲市」があったことを書き留めておきます。
▽日本の宝「月の都」
まとめです。「月の都」が文芸に最初に登場するのは、平安時代前期に作られた竹取物語で、天体の月にある都を意味していました。平安時代中期に作られた源氏物語の中では、月が現れている京の都の意味で使われました。この用法と意味するところは、その後長く続きました。
明治時代になって、更級村初代村長の塚田雅丈さんが、月が特別に美しい歴史文化のまち、という意味に発展的にとらえ直し、京の都から切り離し、古今和歌集の「わが心慰めかねつさらしなや姨捨山にてる月を見て」以来、都人たちがあこがれてきたさらしなの里の呼び名として使うようになりました。
月が出ている京の都を意味する「月の都」は、鎌倉時代初めの藤原定家が月の都とさらしなをセットにした歌「はるかなる月の都に契りありて秋の夜あかすさらしなの里」を詠んだことで、さらしなの里が「月の都」であるという認識が広まっていった 可能性があり、雅丈さんはこの定家の歌を知って、さらしなの里を月の都として地域おこしをしようとしたとも考えられます。
雅丈さんは宣伝や定着の手段として、地元だけでなく東京をはじめ賛同してくれる知識人、明治政府の要人や宮内省の関係者をさらしなの里に招いて、そのすばらしさを体感してもらい、「月の都」の歌をいくつも詠んでもらったのでした。東の都、東都という言葉が盛んに使われるようになって、都の意味が相対化される明治維新という新しい時代の到来も後押ししたと思います。月の都と呼ぶにさわしい実体と歴史を持つのは、さらしなの里だという強烈な自信と自覚が雅丈さんにはあったと思います。
雅丈さんの「月の都」による地域おこし戦略は、電気が暮らしに入って日本人の月への関心が薄れ、戦後は石原慎太郎さんの小説「太陽の季節」がベストセラーになったことに象徴されるように、月よりも太陽への関心が強まる時代となり、とん挫しました。しかし、地球環境問題など人類の存続が脅かされるような心配が支配的な今、再び月への人々の志向が強まっているのは確かです。そういう時代を反映して「月の都」が日本遺産にふさわしい言葉として文化庁に認められ、「月の都千曲」があると思っています。
主な参考文献
「姨捨山の文学」(矢羽勝幸著、1988年、信濃毎日新聞社発行)
「冠着山(姨捨山)のお宝と佐良志奈神社社頭碑からの真実」(大橋静雄、北村主計、2016年、戸倉史談会「とぐら41号」)
「和歌と俳句でたどる月の都の歴史」(大谷善邦、2022年)