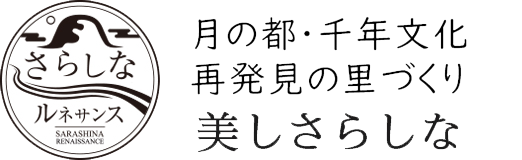「更科」の文字が記された今から約千三百年前の木の札が、千曲市屋代で見つかっています。高速道路の上信越自動車道建設の際に行われた、1994年の埋蔵文化財発掘調査で出土したもので、「府 更科郡司等…」と墨で書かれています(写真左上)。今の長野県庁にあたる信濃の国府から地域の役所である更科郡(現在の表記は更級郡)など、周辺の郡の役所(郡衙)に出した指令が書かれていたもので「国府木簡」と呼ばれます。札の下の部分が欠損しており、指令の内容は分からなかったのですが、 発掘から史料の調査保存整備にあたってきた長野県立歴史館総合情報課長の水沢教子さんが、「指令は当時流行していた疫病への対策だった」という仮説を最新の同歴史館研究紀要第31号(2025年3月発行)に発表しました。飛鳥時代から奈良時代にかけてのさらしなの里の様子がうかがえる大変興味深い論考です。(画像クリックで拡大、ダウンロードできます)
「府 更科郡司等…」と墨書された国府木簡は現在の長野自動車道と合流する更埴ジャンクション直前の上信越自動車道の地下から見つかりました。グーグルアースの空中写真の上部、白い〇枠の所です。発掘中の現場の様子の写真(長野埋蔵文化財センター発行「長野県屋代遺跡群出土木簡」から転載)が右上。西から東を望んでおり、右奥の林の近くに雨宮坐日吉神社(あめのみやにますひよしじんじゃ)があります。発掘現場の右(南)には建設が進む上信越道の盛り土が見えます。
発掘によって、古代この場所には千曲川が流れており、その流路沿いから7世紀後半から8世紀前半にかけてのたくさんの動物の骨や木を加工した祭祀具が出土し、この一帯は当時斎場の機能を果たしていたことが分かりました。「7世紀後半から8世紀前半」は飛鳥時代から奈良時代初め。歴史書の「続日本記」によると、特に8世紀初頭は、天然痘など疫病が全国的に猛威を奮い、信濃でもも流行っているという記述があり、疫病を収めるための祭祀がこの場で営まれていた可能性があるそうです。そうした斎場の一角に、国府木簡は削られたり切断されたりして破棄されていました。
国府から郡役所に出された木簡は群を巡回した後、国府に戻されることになっていたので、この国府木簡は指令伝達の役割を終えて破棄されたことになるのですが、水沢さんは「なぜ斎場に破棄されたのか」という問題意識を持ちました。出土した祭祀具の解釈を進めるうちに水沢さんは、疫病がやはっていた時代なので、指令の内容は天然痘などの疫病への対策を伝えるもので、疫病が終息した後、神への感謝を込めて斎場に流したのではないかと考えるようになりました。
奈良で出土した同時代の木簡(藤原宮木簡)には、更級郡の北東に位置する高井郡から、熱冷ましとして利用できる薬用植物「大黄(だいおう)」が都に運ばれたことが記されているので、信濃の国府周辺には薬の供給態勢もあった可能性があるそうです。このことから、水沢さんは、更級郡をはじめ周辺の郡役所に「大黄」のような薬を処方するようにという指令が国府木簡には書かれていたのではないかと指摘します。今後、出土したほかの木簡の調査が進み切断された部分の板が出てきたり、文献の調査が進むなどすれば本当のところが明らかになる可能性があるそうです。
空中写真の左下の白枠の〇は、更級郡の役所があったとされる千曲市郡地区です。右下の写真は埋め戻されて現在は高速道路となっている現場から南に見える光景。冠着山(姨捨山)がはっきり見えます。古代、斎場の近くには国府の役所もあった可能性があるので、都からやってきた役人も、この景色を眺めていました。都からの道(東山道の支道)は、冠着山の右手にある古峠を通っていました。役人はいずれ都に帰る道だと思いをはせていたでしょう。夜は月もかかっていたでしょう。古今和歌集に載る「わが心慰めかねつさらしなや姨捨山にてる月を見て」も、こうした光景の情報や都人らの感慨が蓄積されて詠まれた可能性があります。
水沢さんの論考「屋代遺跡群出土木製形代による祭祀の具体像」収載の紀要は、長野県立歴史館のサイトの「刊行物」からダウンロードできます。https://www.npmh.net/publication/ (大谷善邦)