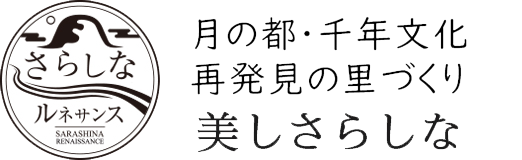2025年のNHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」には、江戸中期の時代や為政者についてユーモアや風刺をもって57577で歌う「狂歌」がたびたび登場しました。ドラマで描かれた時代は、やはりおかしみのある575のリズムの 「川柳」も盛んに作られています。 さらしな姨捨にまつわる狂歌と川柳が載る文献が手元にありました。まず川柳からです。(画像クリックで拡大、印刷できます)
川柳についての文献は、「川柳信濃國」(母袋未知庵著)です。この本は1949年、松本市のしなの川柳社が出版したもので、江戸の川柳雑誌「柳多留」などに掲載された作品の中から信濃(長野県)に関するものを抜き出して編纂しています。信濃の人間ではなく江戸の人間が詠んだもので、その意味で当時の信州人が江戸っ子からどう見られていたかもよく分かる構成になっています。
さらしな姨捨は、やはり江戸でも有名だったのでいくつも川柳が載っていますが、その中ですぐ暗記してしまったのが次です。
月が見て居たので姨を背負い戻し
姨捨山の頂上に母親を捨て置いて村の戻ろとした息子が、月がしっかり自分の行いを見ていることに気がついて、母親を家に連れ帰ろうとする様子を詠んでいます。月を擬人化して人前では恥ずかしことはできないと我に返った息子の真面目さと気まずさが一緒になって苦笑してしまいました。
「川柳信濃國」には、江戸時代の川柳を収集した著者母袋未知庵さんによる解説文もあり、読み応えがあります。それによると、江戸時代、信州から農閑期の冬には江戸に出稼ぎにいく人が多く、そうした人たちは江戸っ子には大飯食いと映り、山の国から来た粗野で鈍重な人間だとからかわれていたことが分かるそうです。そんな信州人の印象を持つ江戸っ子たちの作った川柳が次。
五六杯喰らって伯母を捨てに行き
大食の国は月までたんと見え
田毎程信濃へ団子盛ってやり
2句目と3句目は信濃の国の自慢である「田毎の月」を文字った川柳。大飯食いだから一つしかない月もたくさん見えるんだとか、えらい言われようですが、裏を返せばそれくらい「田毎の月」は江戸でも知られていたということです。
そして、さらしな姨捨にまるわる狂歌です。姨捨文学研究の第一人者矢羽勝幸さんの「姨捨いしぶみ考」からです。二首紹介されています。一つは
姨捨の山のつきかげあはれさにうしろにおひて帰るまで見つ 真顔(まがお)
真顔は「べらぼう」にも登場し、「世の中に蚊ほどうるさきものはなしぶんぶといふて夜もねられず」という倹約を奨励した老中松平定信を批判する狂歌の作者とうわさされた大田南畝の弟子です。地方に狂歌を広めた功労者だそうで、当地への来訪時に詠んだ歌です。
それゆへこの歌も狂歌というジャンルに括られますが、「姨捨の月の光りがあまりにもあはれなので背中に背負って帰りたいほどだ」という心の感動を詠んでいます。「うしろにおひて」の表現が、老婆を山に捨てに行くとき載せる背中のイメージと重なるのでややパロディー色を感じますが、「帰るまで見つ」と続けていることから、何度も振り返って月を惜しんでいた様子がうかがえます。もう一つは真顔の弟子の高住(たかすみ)の作。
入月(いるつき)をおしむ心のあらはれてわが影法師ものびあがりけり
さらしな姨捨の名月が明け方、山に沈んでいくのが惜しくて、背伸びして山の向こう側まで覗きたいくらいの気持ちだったとき、地面に映る自分の影も背伸びしているように感じた心の動きを詠んでいます。これも情景が微笑ましく、まんがの場面が浮かぶ歌です。
これら2首は歌碑となって、松尾芭蕉が立ち寄った長楽寺(千曲市八幡姨捨)の境内にある月見堂の近くに建っています。
(大谷善邦)