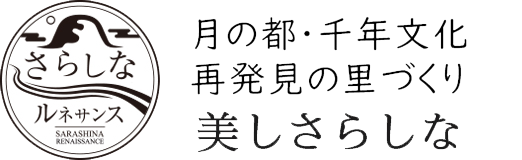日本遺産に認定された千曲市の「月の都」の景観のはじまりのはじまりを体感するウオーキングを5月10日、三峯山(みつみねさん)でさらしなルネサンスと千曲市日本遺産推進協議会の共催で行いました。千曲市の南隣麻績村との境界にある三峯山の40万年前の山体大崩壊によって岩や土が千曲市側に滑り下り、それが現在の「月の都千曲」の主要構成遺産である「姨捨の棚田」になっているので、「月の都」景観のはじまりは、40万年前の三峯山体大崩壊なのです。
同推進協議会からの委託でさらしなルネサンスが編集した「The MOON CITY」では、そのことを紹介していますが、今回は、実際に大崩壊の現場を歩いてだどり、体でも楽しく感じてもらおうと考えました。
参加者約35人の半数以上は、長野市の方。申し込みは須坂市や飯綱町、松本市からもありました。三峯山のふもとの聖高原スキー場のリフトで頂上(1131㍍)に登り、千曲市全域が写った360度パノラマの大きな写真を広げ、三峯山と姨捨の棚田の位置関係がよくイメージできるように見てもらいました。

リフトが到着した峯に「三峯山」の標識が立っていますが、北寄りにある二つの峯と合わせて三つあるので、三峯山という名前になっていると思われます。40万年前の山体大崩壊はこの三つの峯の上に一つの2000㍍級の山があり、それが大雨や地震などで崩壊し現在の三つの峯になっていると考えられます。大崩壊が40万年前という根拠は、黒部ダムがあることで知られる西の方角にある立山の起こした40万年前の噴火の火山灰が、「姨捨の棚田」近辺のボーリング調査で見つかっていることです。
三つの峯は尾根でつながり歩けるようになっており、こうした解説を聞いてもらった後、千曲市側に残る大崩壊の痕跡の「千曲高原カントリークラブ」と「大池」を尾根から眺めてもらいました。尾根の千曲市側は山体大崩壊がうなずける切り立った崖になっています。
約2時間をかけて歩いて〝40万年の旅。心配だった雨は朝方に上がり、気持ちよく歩くことが出来ました。まだ初夏で葉が広がり切っていない時期であるのもよかったと思います。日本列島に人類が到達したのは約4万年前なので三峯山大崩壊の現場を目撃した人はいませんが、今回のウオーキングに参加した方々が、脳の中で目撃、体験できたとすればうれしいです。
三峯山は冠着山(姨捨山)の西に位置し、三つの峯は長野市方面から千曲市に来るとき特徴的にかわいく見えます。向かって一番高い左の峯に「三峯山」の標識が立っていますが、右の二つの峯にも名前、愛称をつけたらどうかと言う人もいました。まとめて「峯3きょうだい」というのもいいかもしれません。

写真はいずれも、千曲市日本遺産センターのスタッフ丑丸久美さんの撮影です。