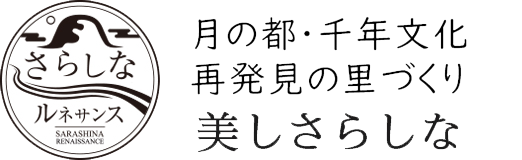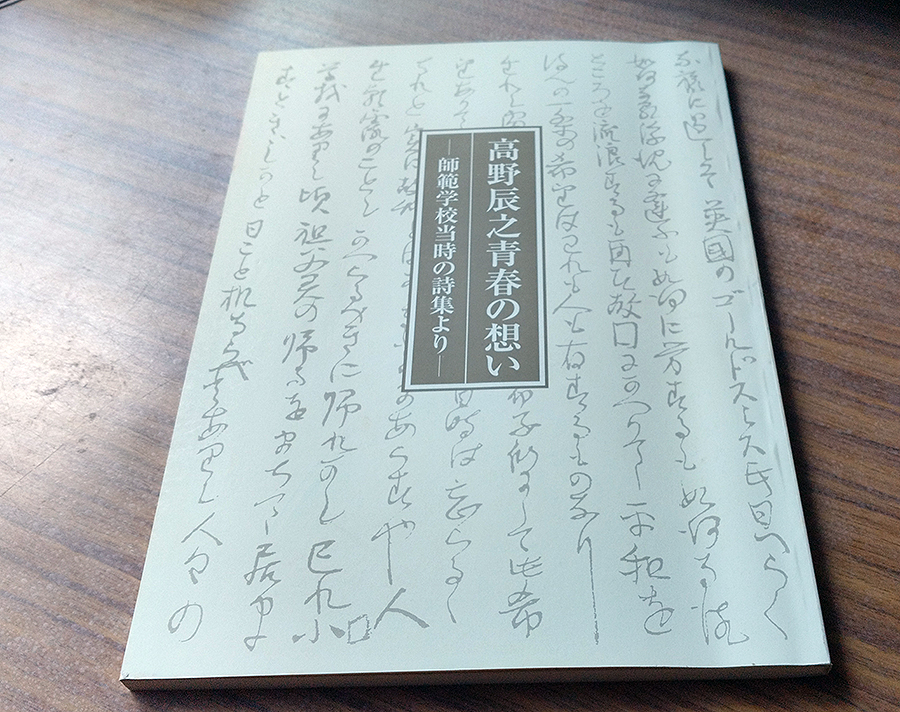
文部省唱歌「故郷」「春の小川」の作詞者である豊田村(現長野県中野市)出身の高野辰之さんが20歳のとき、当地で初めて月見をしたことについて書いた「更科の月」という詩文があります。豊田村が発行した「高野辰之青春の想い 師範学校当時の詩集より」に収載されています。先生になるために師範学校で勉強していた明治29年(1896)の中秋9月21日、長楽寺境内(千曲市八幡)で「更科の月」を味わったその感慨を文学者ならではの表現で記述しています。「更科の月」がどれほど高野さんのあこがれとなっていたか、また人々にとってどれほど月の出が楽しみだったかがよくうかがえる報告文でもあります。
中秋の一日、朝起きてから夜寝るまでをしたためたものですが、それほど長くないので、全文引用します。文語体は…という方は、後に書いている読み解きをさきに読んでみてください。(大谷善邦)
「更科の月」 高野辰之
人生固(もと)より恨事(こんじ)多し。
今宵もまた恨みてのみや過ごすらんとは
明治廿九年九月廿一日の昼つ方のこころ也けり
こよひぞ 中秋の月といふ日の心なりけり
更科や姨捨山にとび行きて山の端(は)にほのめくより見ばやさんとて
朝とう目さむる直に
空仰ぎたりしに青天のかぎり一点の雲影だになかりしを
昼近くより東の山々にあやしう雲見えそめぬ。
吹き払へや秋の風こころしあらば月の為(た)めと念ずれど、
あらむともせざりしかど
定めの時よりいたう後れぬる汽車のさりともと気遣いたるに
怨(うら)みをも乗せて向ひぬ。
至りつきしは五時半過る頃也けり。
姨石の上面影堂月見堂などは文人どもうごめくらむ。
色紙・短冊など商ふものそこそこから充ちたる。
そがひの山峯より尾までひとならぬはなし。
紛(まぎ)れ居らむにはと思ひ居る頃、
峯よりして拍手の音は聞こえそめぬ
亢龍(こうりゅう)の悔(くい)あらむもとて中腹に止まりし身の少しは口惜しきに
手は愈々(いよいよ)下りて己等もおもわず打ちぬ。
心許(こころもと)なくのみおもひし雲は次第にうすれて
こころありがほに遠のきし鏡台山(きょうだいさん)頂(いただき)より
一条の銀線あらわれしが新月となり、弦月となり、
やがて白かねの鏡かけたらんさまにさし出てぬ。
一弓上り二弓上る清宵(せいしょう)の空 拍手の声呼号の響に恐れてや、
雲はますます月のさす手を退けば、
円満とはこれらをやいふらんと思わるるのみ、
言(こと)の葉(は)などの更に出づべくもあらず。
おのもおのもあなといひあわれと叫ぶのみにて
しばしは月にしづまり果てぬ。
愈々(いよいよ)上るにつれて小さくこそなりたれ、
色はあからみまさりて
秋風浮雲を払へば物苦しき迄にさやか也
あはれ限ある人の手に写されぬこそ貴けれどおもひてもとより
言の葉なき身のくちあらば一入(ひとしお)重うなりまさりぬ
山なせる人々には上るを見たればとてかえるもあり、
入り方迄見んというもあれど
七里の途(みち)をたどるべき身は目を閉ぢて山を下りぬ
葉ごしの月光に浴し清流の影にほほゑみ
橋上に立ちて傾き行くを忍べば
月又我を語らわんとてたゆたふものごとし
幾重の山 いくその里をへて迎えたる月に
かへる閨(ねや)の内迄送られぬ
閉ざさんとして名残惜しめば何処(いずこ)よりあらわれけむ
一抹(いちまつ)の雲、月の面(おも)わを覆ひけり

冒頭の「人生固(もと)もり恨事(こんじ)多し」という書き出しがまず興味深いです。中秋のころは雨が降りがちでなかなか名月を見ることが難しかったので余計人々のあこがれは高かったのですが、高野さんは師範学校を卒業する前になんとして実物を見たかったのだと思います。さらしなの里姨捨で「山の端から現れる月を絶対見るんだ」と期待して朝早く起き、「空は雲一つもなくラッキー」と思いました。しかし、昼頃になると、月が上る東の山々に雲がかかり始めました。その様子を見て高野さんは冒頭に「人生固より恨事多し」と、「今年もまた更科の中秋月は見られないのか」と恨みごとを言いたい気分になったのです。
さらに高野さんを心配させたのが汽車の遅れです。1896年は長楽寺の最寄りの姨捨駅は開業していなかったので、長野から信越線で出発、屋代駅(1888年開業)で降りたと思います。屋代駅からは長楽寺まではさらい時間がかかるので、月の出に間に合うかはらはらしていたに違いありません。
それでもなんとか夕方5時半ごろに長楽寺に到着しました。2024年の中秋9月17日の月の出予測が午後6時前であるように、毎年「更科の月」の出はこの時刻頃なので、高野さんも間に合いました。着いてみたらびっくり。巨岩の姨石の上はもちろん、本堂、月見堂などは人でいっぱい。色紙や短冊を売る人もたくさんいました。
この人たちの中になんとか入って月の出を眺めたいと思っていたら、拍手が聞こえてきました。月が出る東の方角を見ると、空の雲がだんだんと晴れていき、鏡台山の峯から「一条の銀線があらわれ、それが新月となってさらに弦月となり、やがて欠けているところがない白い鏡のようになって出てきた」と高野さんは描写しています。更科の中秋の月を幾度となく見てきた経験を踏まえると、この描写はよく分かります。夕方とはいってもこの時季はまだ少し明るいので、月は白っぽく現れます。「一条の銀線」の「銀」は白い月の姿の一片が見えた様子。それが鏡台山の峯のカーブにそって三日月型の新月の形となり、さら上って半月のようになります。山の端からの月の出を見ることは、誕生から大人になるまでを一度に見る体験とも言えます。
高野さんはその様のすごさを表現する「言葉など出てこない。みんな、ああと感嘆の声を発するだけで、静まりかえっている」と続けています。
空に上がってからも「更科の月」を見続けたい高野さんでしたが、師範学校のある長野までは「七里」もあって遠いので、帰らざるを得ないことが残念でした。
しかし、長野に戻って「更科の月」を名残惜しみながら寝ようとしたら、薄雲がかかっている満月が夜空に浮かんでいました。その様子にさらに感激したのではないかと思います。早朝から夜更けまで「更科の月」にたっぷりひたった高野さんの気持ちや思いが伝わってきます。(大谷善邦)
*高野辰之さんが見た「更科の月」は、「汽笛一斉新橋を…」の歌詞で知られる「鉄道唱歌」作詞者で文学者の大和田建樹さんも同じ日に、別の場所で眺めていました。大和田さんもそのときの文章を残しています。別の機会にあらためて紹介します。