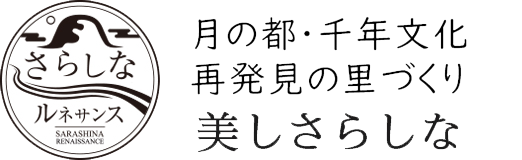さらしなルネサンスは9月22日、第2回さらしな学わくわく講座を千曲市の姨捨観光会館で開きました(約50人が参加)。今年は、松尾芭蕉がさらしなの里に来て330年となるのを記念して、私たちが普段使う言葉の意味を掘り下げ日本人の心の在りようを明らかにしてきた東京大学名誉教授の竹内整一先生に講演をお願いしました。竹内先生は2014年、当会のキックオフ集会で、「わが心慰めかねつさらしなや姨捨山に照る月をみて」の和歌が都人たちに与えた衝撃のメカニズムを解き明かしました。今回は「風とかなしみ」という演題で、芭蕉の「さらしな紀行」を取り上げました。
さらしなルネサンスは9月22日、第2回さらしな学わくわく講座を千曲市の姨捨観光会館で開きました(約50人が参加)。今年は、松尾芭蕉がさらしなの里に来て330年となるのを記念して、私たちが普段使う言葉の意味を掘り下げ日本人の心の在りようを明らかにしてきた東京大学名誉教授の竹内整一先生に講演をお願いしました。竹内先生は2014年、当会のキックオフ集会で、「わが心慰めかねつさらしなや姨捨山に照る月をみて」の和歌が都人たちに与えた衝撃のメカニズムを解き明かしました。今回は「風とかなしみ」という演題で、芭蕉の「さらしな紀行」を取り上げました。
「風の谷のナウシカ」にも影響
キックオフ集会の講演で、竹内先生は和歌の「慰めかねつ」という表現に着目し、美しいさらしなの里の月をみても、心のかなしみはどうにも慰めることができないと歌うその理由を解説しました。老いて死ぬことのかなしさ、さびしさはどうやっても慰めきれないが、しかし、慰め続けるしかなく、そうしたかなしみを表現することでこそ救われるのだということでした。
22日の講演で竹内先生はこのかなしみについて、さらに発展的に語りました。芭蕉がさらしなの月をみたくなった理由について「さらしな紀行」の冒頭、「しきりにすすむる秋風の心に吹きさわぎて」と書き、風のしわざであることに着目しました。風は、奈良時代より前は生命のもとと考えられ、受胎するとも考えられており、続く時代の人たちもそうした風の、命にかかわる力のありようを受け継ぎました。近代では宮沢賢治の「風の又三郎」、現代も宮崎駿監督の「風の谷のナウシカ」に影響が及んでいるといいます。
「あわい」にあるさらしなの里
「秋風」について記した芭蕉の文章としてはほかに「野ざらし紀行」があります。そこでは泣いている捨て子のもとに吹く秋風のことを描写しています。捨てられてかなしいだろう、しかし、両親はお前をにくんでいるわけではない、自分の身のかなしさを泣き続けよ。そして、秋風の中で泣く捨て子の声はかなしく人の心を責めるものだ、という意味の句を添えています。
竹内先生の講演を聞き、秋の風とかなしみは相性がいいというか、切り離せない関係であることがわかりました。竹内先生は最後に、そうした風とかなしみにまつわる表現の場として、さらしなの里が選ばれた理由を語りました。さらしなの里は聖と俗、自然と人間の生活の「あわい」の織りなす風景だといいます。「あわい」とは、向かい合った二つのものが交わるところのこと。さらしなの里のある千曲市は、中央を千曲川が流れ、鏡台山から上った月が対岸の冠着山(姨捨山)方面に沈みます。芭蕉が訪ねた長楽寺からはその景色がそれほど遠くなく身近な感じで見ることができます。そのことが重要で、聖の景観と人間の生活がうまくまじりあっていると竹内先生は指摘しました。竹内先生の講演を聞き、だから、大勢の歌人がさらしなの里の歌をよみ、都人のあこがれの地になったのだと思いました。ひれ伏さざるをえないような景観であれば自分に引きつけた歌はつくりづらいと思います。
会場にも吹きぬける秋風
竹内先生の後ろの屏風は、千曲市倉科出身の日本画家、故倉島丹浪先生の「姨捨山」という作品。木花開郤姫(このはなさくやひめ)という神の物語をモチーフにしたもので、地元のお寺(長楽寺)に伝わる縁起(物語)では、木花開郤姫が醜い心を持つおばさんの神(大山姫)と一緒に、月が美しく見える信濃の山を訪ねます。おばさんはこの月を見て、醜い「姨の心」を捨て、清らかな心になったので、山は「姨捨山」と伝えられるようになったというお話です。竹内先生の講演を聞いているうちに、演台を飾ったススキの穂と一緒にこの絵の中にも秋風が吹きぬけていくようでした。
竹内先生のキックオフ集会の講演内容はここをクリックしてご覧ください。(大谷善邦)